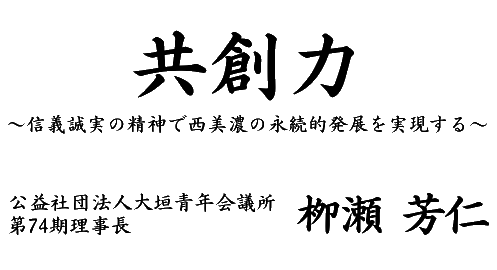

2025年度(第74期)基本方針
- 1.信頼関係を大切にして共創型リーダーを育成する
- 2.地域みらいビジョンを見据えて西美濃を共創する
- 3.多様なネットワークを活かして共創関係を深める
- 4.会議の質を高めて共創意識を向上させる
- 5.共感を呼ぶ拡大運動で共創の輪を広げる
【はじめに】
2025年は、1945年の第二次世界大戦終結から80年になります。戦前から有数の工場地域であった大垣市は、戦時中に合計6回もの空襲に見舞われました。1945年7月29日の大垣空襲では約2万発もの焼夷弾等が投下されて市街地は焼け野原となり、当時国宝だった大垣城も焼失しました。当時の大垣の方々は、家族を失い、家を失い、故郷のシンボルまで失って、失意のどん底にあったに違いありません。
大垣青年会議所は、このような大垣空襲からわずか 7 年後の 1952 年、35 名の先達によって全国で25番目の青年会議所として設立されました。戦後の混乱期という想像を絶する暗闇の中で、日本及び世界の繁栄と平和に寄与することを目的として掲げ、TRAINING(個人の修練)・SERVICE(社会への奉仕)・FRIENDSHIP(世界との友情)の三信条のもと未来を自らの手で創ることを力強く宣言されたのです。 この決意と情熱は、戦後の西美濃を照らす希望の灯となり、先輩方の不断の努力によって73年間受け継がれてきました。大垣青年会議所の会員である私たちには、歴史を繋いでこられた先輩方に感謝し、託された希望の灯を消すことなく更に次代に繋げていく責務があります。
戦後80年という節目を迎える今年度、あらためて創始の精神に思いを致すと共に、青年会議所の理念である明るい豊かな社会を創るため、一青年として現在の社会課題に全力で向き合っていきましょう。
【共創力とは】
現在、私たちは、将来予測が困難な時代を生きています。新しいテクノロジーやSNSによる社会構造の変容、ロシアのウクライナ侵攻やイスラエルのパレスチナ攻撃、歴史的な円安と物価高、能登半島地震等の激甚災害、超高齢化社会と2025年問題など、様々な社会課題が複雑に絡まって将来予測を困難にしています。これに伴って私たち自身の価値観もかつてない速さで変化しています。
このような混沌とした時代、私たちは明るい豊かな社会を創るためにどのような運動を展開するべきでしょうか。私はその答えを共創(Co-creation)に見出します。共創とは、多様な立場の人たちが対話しながら新しい価値を共に創り上げていくことを指す言葉です。もとはビジネス用語で、企業が顧客の意見をもとに新商品を開発する場面などで用いられていました。しかしながら、今や共創の概念は大きく進化しており、企業と企業が一緒に新しい事業を行う事業共創、企業と行政がアイデアを出し合う官民共創、異なる世代の人たちで持続可能な社会を目指す多世代共創も生まれています。共創によって新しい手法を次々と創り出すことができれば、その中から複雑な社会課題を解決する手法を見つけることもできるのです。
もっとも、共創の考え方は、私たち大垣青年会議所にとって目新しいものではありません。もとより、大垣青年会議所は、20歳から40歳の出自も仕事も異なる多様な会員同士が議論し、社会課題を解決するための手法を創り出してきました。過去の事業を振り返ると、住民が参画する「まちづくりコンテスト」から生まれた「ツール・ド・西美濃」において、各行政や関係各諸団体の方々と協議を重ね、官民一体の広域事業を行ってきました。大垣青年会議所は、これまでも西美濃の共創の場で在り続けてきたのです。ならば私たちも大垣青年会議所を学び舎とし、その活動や運動に精一杯打ち込むことで、共創を実現していくための力である「共創力」を高めることができるはずです。会員一人ひとりが共創力を発揮して、現在の社会課題から目を逸らすことなく正面から挑んでいきましょう。
【信頼関係を大切にして共創型リーダーを育成する】
青年会議所は、JCI Missionにある通りにリーダーシップの開発と成長の機会を提供してくれます。現在のJCI Missionは2022年に改定されたもので、新たに「leadership」を追加することによって、青年会議所が世界で活躍できるリーダーを育成するための組織であることを明示しました。将来予測が困難で価値観がかつてない速さで変化する世界。今までの正解がいつの間にか正解ではなくなるような時代。私たちが生きる現在には、多様な立場の人と対話して共感を生み、新たな正解を共に創ることができるような共創型のリーダーが求められているのではないでしょうか。そして、共創型のリーダーになるためには、コミュニケーション能力の向上はもちろんのこと、それ以上に信頼関係を大切にしながらリーダーとして成長することが必要になると考えます。
青年会議所は、会員一人ひとりが成長を目指して修練を積む場所です。周囲から信頼されるリーダーになるためには、まず自らを鍛え磨く必要があります。家庭や仕事に加えて青年会議所の活動や運動を行う日々、時には投げ出したくなることもあるかもしれません。しかし本当に投げ出してしまえば、今度はそれまで支えてくれた仲間の信頼を失う結果になってしまいます。他方で、家庭や仕事を疎かにすれば、家族や職場の信頼を失うかもしれません。あらゆる信頼関係を大切にするために己を律して必死で考え行動する。それは決して楽なことではありません。それでもこのような修練を重ねていると、あるとき今までの考え方や行動を上手に変化させて前に進む道が見えてきます。それは、時間の使い方の見直しであったり、仕事上の工夫であったり、精神面の変化かもしれません。この前に進む道を見つける体験こそが大きな糧となり、リーダーとしての成長に繋がるのです。
青年会議所は、目的意識を持って成長を望めば望んだ分だけ成長の機会を与えてくれます。時代に求められるリーダーになるため、今こそ自分を見つめ直し、信頼関係を大切にしながら一緒に成長していきましょう。
【地域みらいビジョンを見据えて西美濃を共創する】
私たちが描く未来の西美濃とはどのようなまちでしょうか。将来予測が難しい現代では、最初に実現したい未来像であるビジョンを描き、そこを起点に逆算して課題解決を考えるバックキャスティングが求められています。つまり、まずビジョンを共有してから運動を展開していく流れが重要になるのです。
大垣青年会議所は、2010年代運動指針であった「『地球的価値』の田園都市構想~西美濃の心が一つになる瞬間へ~」を2019年に恒久的指針とし、長期ビジョンである「地域みらいビジョン」を策定しました。また、2021年には西美濃地域2市9町の各行政と社会福祉協議会の3者で災害時における協力体制の協定書を締結し、これを踏まえて2022年に短期ビジョンである「最重点ビジョン」を策定して、2023年から2025年まで「災害を見据えた広域連携に向けた取り組み」を行うことを決めました。このような流れの中、大垣青年会議所は過去3年間で防災意識の向上を目的とした事業を実施してきました。今年度は短期ビジョンの最終年度として総まとめの年になります。近い将来に確実に起きるとされている南海トラフ巨大地震を想定しながら、広域連携事業としてより実践的な防災に対する体験学習を行うことで更に西美濃地域に防災意識を根付かせていきます。
また、「地域みらいビジョン」を推進する上で郷土愛の醸成は不可欠と言えますが、そもそも私たちは自分の住み暮らす西美濃地域をどれくらい知っているでしょうか。観光庁は2025年開催の大阪・関西万博等を起爆剤にインバウンド戦略を進め、高付加価値で持続可能な観光地域づくりに取り組むとしています。今年度は、これを好機と捉えて西美濃地域の歴史と魅力を学び直すと共に、他団体と協働して西美濃地域の魅力を地域内外に発信していきます。
更に今年度は、大垣青年会議所による2023年から2025年までの運動を検証して2026年以降の運動をどのように展開していくかを決定します。そのために「地域みらいビジョン」について理解を深め、多様な立場の意見を踏まえて、バックキャスティングによって短期ビジョンの策定を進めていきます。
【多様なネットワークを活かして共創関係を深める】
大垣青年会議所は多様なネットワークを持っています。このネットワークとは人と人との繋がりであり、その繋がりの数だけ共創関係を構築することができるのです。もっとも、大垣青年会議所の持つネットワークを十分に活かすためには、その内容と価値をしっかりと理解することが大切です。
まず、全国・全世界の青年会議所とのネットワークがあります。これは、大垣青年会議所を円の中心として岐阜ブロック協議会、東海地区協議会、日本青年会議所、国際青年会議所と広がる繋がりで、各組織の事業に参加して友情の輪を広げたり、役員や委員として出向して無二の経験を積むことができます。昨年度、私たちは岐阜ブロック協議会の主管という貴重な経験を積み、他の青年会議所との関係を深めることができました。この経験を活かすと共に、今年度も出向の機会を大切にしながら大垣青年会議所以外の事業に目を向けて、自ら進んで発展と成長の機会を掴み取りに行きましょう。
次に、花蓮國際青年商會と姉妹JCとしての交流があります。この交流は、国際理解と親善を助長する上で重要な機会となっています。花蓮は昨年4月の台湾東部沖地震で大きな被害を受けました。大垣青年会議所では、お見舞いメッセージを表明し、大垣JCシニアクラブ会員の先輩方のあたたかいご支援を賜って災害義援金を送らせて頂きました。残念ながら昨年度は姉妹締結55周年を台湾の地で迎えることができませんでしたが、お互いの絆を再確認することができました。今年度は、花蓮國際青年商會創立60周年になりますので、周年事業を通じて姉妹JCの絆をより強くしていきます。
更に、西美濃地域の他団体との交流があります。今年度、大垣青年会議所は、大垣市青年のつどい協議会の加盟団体として会長を輩出します。大垣青年会議所の役割を理解し、様々な事業に積極的に参加・協力することで、他団体のメンバーとの交流を深めながら地域の期待に応えていきましょう。
加えて、今年度は大垣青年会議所の活動や運動に関する広報を強化します。広報ツールの運用を見直してより効果的な広報を行うことで、新たな人と人との繋がりを生み出して共創関係を構築します。
【会議の質を高めて共創意識を向上させる】
大垣青年会議所は、これまで73年間、明るい豊かな社会の実現を目指して活動や運動を展開しながら最も適した組織の在り方を模索してきました。青年会議所は40歳までの年齢制限と、組織や役職の単年度制を最大の特徴としており、このシステムによって毎年のように新陳代謝が行われます。その中で歴史を重ねて現在まで踏襲されてきた組織、制度、規律には、今までそうしてきた理由があるはずです。ドイツのオットー・ビスマルクの格言に「愚者は経験に学び、賢者は歴史に学ぶ」という言葉があります。自分の経験だけに頼らず、先輩方が経験した歴史を含めて考える必要があります。
現在、大垣青年会議所は、会員数の減少によって少人数での運営を余儀なくされています。また、テクノロジーやSNSによって社会構造が変容し、私たちの価値観もかつてない速さで変化しています。こうした現状の中、変えてはいけないものを守るためにあえて何かを変える選択をすることもあるでしょう。ただ、岐路に立ったときは、今までそうしてきた理由を踏まえながら、会議によって正解を創り出さなければなりません。例えば、大垣青年会議所の法人格の在り方についても、公益法人格を取得した背景と目的を理解し、全会員による会議によって議論を進める必要があります。会議は、青年会議所の原点であり出発点なのです。だからこそ、私たちは、会議を単なる儀式で終わらせるのではなく、会議の質に徹底的にこだわる必要があります。質の高い会議を行うことは、立場の異なる相手方と真剣に対話する経験となり、その経験がより高い共創意識へと繋がっていきます。
会議の質を高めるためには、正確かつ円滑な会議運営を行うと共に、大垣青年会議所の会員一人ひとりが主体性を持って会議に参画して活発な議論を行う必要があります。そのためには、会議を行う時間だけにスポットを当てるのではなく、普段から大垣青年会議所全体で活発な交流を行うことが大切です。会員同士で声を掛け合い、委員会に積極的に参加し、議案の作成に関わって、全ての会議を自分事と捉えて参画していきましょう。
【共感を呼ぶ拡大運動で共創の輪を広げる】
大垣青年会議所の正会員数は現在50名を下回っており、今年度は更に8名が卒業する予定です。青年会議所の運動は「ひとづくり」と「まちづくり」と言われています。青年がお互いに切磋琢磨して成長し、その青年が地域に影響を与えていく。青年会議所の運動は会員一人ひとりの手で支えられています。だからこそ、会員数が減少すれば運動の低下に繋がっていきます。大垣青年会議所にとって会員拡大は急務であり、各委員会の枠を越えて全会員で取り組まなければならない重要な課題です。
しかしながら、会員拡大とは、ただ会員数を増やせば良いというものではありません。現在は多様性の時代と言われ、あらゆる団体で多様な人財の活躍が求められていますが、多様性を口実に何でも自由を許せば組織としての伝統や秩序は崩壊していきます。大垣青年会議所は、嵐の中を進む帆船のようなもので、会員一人ひとりが同じ目的地を目指して船に乗り込み、各々が与えられた役割を果たすからこそ前に進むことができます。同じ目的地を目指して一緒に汗をかいてくれる仲間が必要なのです。そのような仲間を一人でも多く私たちの船に乗せて、全会員で航海の感動を分かち合いましょう。
日本青年会議所は、2021年から2025年までの5ヶ年計画で理念共感グランドデザインを策定して理念共感拡大に取り組んでいます。理念共感拡大とは、理念に共感した多くの青年に青年会議所に入会してもらう取組みになります。もっとも、候補者に対して一方的に青年会議所の理念を伝えるだけでは共感を得ることはできません。まずもって候補者の立場に立って対話をし、候補者が本当に求めているものを的確に把握し、そこに青年会議所の理念と魅力を重ね合わせて寄り添うことで初めて共感が生まれるのです。そのためには、会員一人ひとりが大垣青年会議所の理念と魅力を自らの言葉で語れるようになる必要があります。共感を呼ぶ拡大運動によって様々な立場の候補者を私たちの運動に巻き込み、共創の輪を大きく広げていきましょう。
【信義誠実の精神で西美濃の永続的発展を実現する】
多様な立場の人たちが対話しながら新しい価値を共に創り上げていく共創。その源泉は、お互いの信頼関係にあります。信頼関係がなければ異なる立場の人たちと対話することはできませんし、ましてや共感を呼んで共に新しい価値を創ることはできません。では、そもそも共創の基盤となる信頼関係とは何を意味するのでしょうか。
民法第1条第2項は「権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行われなければならない。」と定めています。これは、社会生活を送る上で他者の信頼を裏切ったり、不誠実な行動をしてはならないというルールで、信義誠実の原則と呼ばれています。民法は社会生活上の基本的なルールを定めた法律であり、あらゆる法律の基礎になっています。その第1条に定められた信義誠実の原則は、私たちの社会の根本的なルールと言えるかもしれません。
しかしながら、信義誠実の原則は、あくまでも人と人を拘束するためのルールです。拘束とは制約を意味するものであり、相手を制約しても共に新しい価値を創ることはできません。私は、このことを大垣青年会議所の活動や運動を通じて学んできました。人はたとえルールで拘束したとしても自発的に動いてくれません。私たちが真に必要とするものは、人と人を拘束するためのルールではなく、人と人を繋ぐための精神なのです。人と人を繋ぐために、相手の信頼を裏切ったり不誠実な行動をしないようにする。いつも相手の立場に立ち、相手の考えていることを想像し、思いやりの心をもって接していく。私は、そのような信義誠実の原則を超えた「信義誠実の精神」を何よりも大切にするべきだと考えます。
信義誠実の精神は、人と人とを繋ぐ架け橋となり、共創力の源泉となります。大垣青年会議所の会員一人ひとりが共創力を発揮してその手で西美濃の未来を創り出すとき、きっと西美濃の永続的発展を実現することができるはずです。さあ、一緒に、未来を創りましょう。
